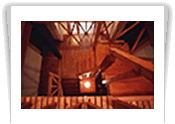リホームでパッシブソーラーは可能?
弊社の設計しました「AUT・AUT」という住宅がありますが、それをこの度リホームすることになりました。そこで、この家は地下室から吹き抜けが2階まで連なるというぐらい空間が大きいため、パッシブソーラーによる循環システムを一度考えてみようと思うのです。勿論こちらも調べているのですが、どなたか良い情報(経験工務店等)をお持ちの方がおられたらご連絡もらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
老人力
「今日はいかないん?」、「ああ一仕事終わったら後から行くよ」。道端で出会った近所仲間が交わす日常の何気ない会話である。日当たりのいい日には、このほのぼの?した会話は今でも田舎なら聞こえて来そうである。村はずれの集会所にあるゲートボール場へ行く途中の場面である。なんとものどかな風景であり、みんな楽しそうに見える(見えた)のがうれしい。これは、子供の頃の記憶にある良き時代の田舎の風景である。いわゆるひと昔、いやふた昔前までは、年寄りから子供までいろんな世代の人々が一緒に、あるいは同じ空間で生きていた。
翻って現代、巷ではワンルーム老人専用マンションが流行っているが、そこに展開されているのは、利殖追及が命題であり、決して豊かな空間になっているとはいえないだろう。言葉は悪いが一種の詰め込みであろう。
片や、昔(1980年代だと思うが)「ライフイン京都」という若林さんの傑作があった。なんとも豪華なイメージを思い出すが、今にして思えばその後の豪華「老人ホーム系」のさきがけのような建築だった、前述のマンションとまったく違うのはめくるめく豪華さだ。それは現代ではホテルのロビーのような瀟洒な空間、としたイメージに移り変わってきているが、少なくとも老人のための施設には見えない。
この両極端な建築を必要とする社会を高度に発達した21世紀のわれわれは作ってしまったのである。
21世紀的合理社会では、どうしても社会の中のバランスが極端に崩れているとしか思えない。勿論単純に人口分布が崩れて来ていることも一因だが、根本は、いい意味のヒエラルキーの欠如が主な原因であろう。結果現代は、極端に世代混在のなくなっている社会なのである。いきおい、老人自体も自信と活力を失い、延命された寿命をもてあまし、抜け殻のような余生を送るだけになる。どうも発想が貧困なのか、僕にはそういうイメージしかわいてこない。これでいいのだろうか・・・。
老人はいい意味での「怪人」になるべきではないだろうか。怪人になって世の中を闊歩すればよい。勿論どうしようもない頑固老人は願い下げだが、若い社会からお払い箱のような生き方を受忍して欲しくない。せっかくの生命力を生き生きと生かして欲しい。
今年100歳だという「オスカーニーマイヤー」(ブラジル)が新作を作ったのだと言う。その建築がまたカッコいいときている。これはすごいなと言う感じのものである。村野さんの現役94歳をはるかに越えている、脅威のエネルギーである。この老人力いうか怪人ぶりは、少なくとも世の老人たちにに元気を与えてくれるのではないか。
メールアドレス変更の件
訂正です、すみません。
サーバーアカウントのメールアドレスは変わりましたが、
公には取得ドメインのアドレスですから、皆様の方からは現アドレス(archi@nitta-masaki.com)
のままでも結構のようです。
不慣れを露呈してしまいました。
お騒がせしました、申し訳ございません。
メールアドレス変更
新年明けましておめでとうございます。
皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。
早速ですがお知らせです。
このほどメールアドレスを変更しました。
2009,1/1よりメールを頂いた方にはご迷惑をおかけしました。お手数ですがもう一度下記の新アドレスに送信お願い致します。
また本日(1/13)以降、メールは下記の新アドレスになりますので、どうぞデータの変更をお願い致します。
<新アドレス>
masaki-nitta@dream.jp
以上皆様にはお手間をお掛け致しますがどうぞ宜しくお願い致します。
アウトサイダーアート
人間の三大欲として良く言われるものに食欲、睡眠欲、性欲がある。それらはみんな人類が長らくこの地球上に生存するための必需欲として「神」から備わったものだろう。しかし本当に人間が人間らしいのはその欲求から派生した習性によってである。音楽を奏でる、絵を描く、文字を読む、物を作る、その他、これらは基は生存のための意思,感覚の伝達技術が発達してきたものである。そして現代においてはこれら派生した「欲」の占有率が、先の生存にとっての三大欲を上回るほど、極端にそのパーセントを上げる人間まで出てきている。いわゆる「オタク」などはその典型で、子供、大人を問わないゲームオタクから、会社、仕事オタク、フィギアオタク、その他よろずオタクブームである。ただこれは何も否定的な現象ではなく、一生懸命の裏返しなのである。言い方が違うだけで、ノーベル賞学者などは「超オタク」でもある。何かに没頭すること、している様は美しいものである。その魅力の源泉とは何だろう、それは常時の意識を超える境地、言い換えればトランス状態かも知れない、それをを覗きたい、覗けるかも知れない未知の魅力があるからなのだ。ピカソ等の天才などもその典型であるが、ここで取り上げたいのはアウトサイダーアートである。スイス、フランスなどから、その魅力、秀逸さの発見、見直し、に火がついたようである。何回か作品を見たのだが確かにすばらしい。
その尽きないエネルギーの発散模様は到底一般人にはまねが出来ない。ではなぜそれが美しいのかと考えた時、一番に思いつくのは無垢さであろう、この言い方は問題があるのかもしれないが、誤解を恐れずに言う。これは本来的に人間に備わっていた遺伝子である。子供のときの絵などがその典型なのは指摘するまでもないが、驚異的なのはやはりその「ひたむきさの持続」なのであろう。これが現代人には決定的に欠けてきた。ゆえにそうした芸術に触れると、あるいは発見すると余計に感銘の度を増し、人間が発展するために身に着けてきた技術にまったく反比例する情熱に感じ入るのである。一言で言えば合理主義を完全に凌駕していることに感動するのだと思う。考えてみると、建築バカという言い方もあるくらいで、建築家も一種のオタクかもしれない。だとしたら、現代の建築も、人々に、合理主義を超えた感動を与えられるほどのものとして、またせめて、それを作って見せれる「超オタク」人であるべきではないのだろうか。