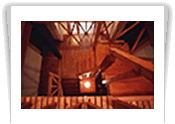造形
ガウディーやゲーリーを持ち出すまでもなく、人間が、無謀にも唯一自然界に挑戦出来る、あるいは景観美を挑める情熱(技術)が造形力である。それは人間という動物が生命力を誇示する[術]として表出しうるエネルギーでもある。生命力がないときは造形欲が凪いでしまう。戦後の荒廃した日本、近くは阪神大震災時の、急ごしらえの復興建築のありようを見ればわかりやすい。バブル社会は確かに愚かしいが、こと建築、あるいは文明にとっては一概にもそうは言えないところがある。バブルとその生命力には共通する[因子]が存在しているからだ。たとえば、世界遺産を持ち出すまでもなく、時の権力,財力(バブル)の生命力は,得てして高く、高く(ニューヨークの摩天楼等)空へ向かう破天荒な傾向になるが、それらが後年人類史の中では、建築遺産として認知されるにいたることにもなるから、時代の流れとは「アイロニー」を争う場でもある。果たして21世紀型?バブル「ドバイの実験」はいかに・・・・。
ところが人間面白いもので、大きく立派な箱(物)を作れば作るほど、自分の有限性と内面性の葛藤を同時に抱えてしまう。天下人にまで上り詰めた秀吉の生ざまはまさしくそれの典型のようなものだから、逆に言うと永遠の反面教師として生きつづける。それは目に見えないものの価値を見出したときから始まる。自分は天下人である、しかし、その自分にどうにもひれ伏さない利休に対する嫉妬は尋常ではなかったのだろう。最後は命にまでメスを入れさせたのだから。
人間の心が向かう果ては、どちらの振幅にしろ自力では止められないのか。ほぼ100年ほど前のロシア激動時に見られる芸術運動にも、人間の生命力と知力の結晶が、タートリンとマーレビチという二人の芸術家の作品に対比的に現れる。人間の湧き上がる生命力を表現したタートリンと、逆に内面の審美へと限りなく沈降したマーレビチ。この二人による「究極の間」はロシアアバンギャルドが作り出した最高傑作といえるであろう。確かに、100年後の今日にも同様の状況が見え隠れするし、、またこれから先も、人間が抱える希望と絶望の体内時計として状況を刻む。
神秘
田舎育ちということもあり、夜空が好きである。この冬久しぶりに夜空を見上げた。田舎の夜は何にもなくて、いやが応にも星空が目に入るだけなのだが・・・。そもそも都会でいると夜空、それとも星空を見上げるというような気分になかなかならないもの(自分だけなのか?)。都会では、人々はみんな坂本九の歌のようには生きていない。都会人は星空を見上げる人種ではないのである。以前作品を発表(桂馬の家)した時、「1メートル四方の自由」というコメントをつけたことがある。その時のモチベーションの問題はともかく、都市社会のアフターファイブならぬほっとする瞬間のことである。暗闇で獲得できる?少なくとも自分の周囲1メートル四方の、つかの間の自由と孤独の占有感の話だったと思う。これは確かに、物理的な夜の空間と、心の空間が共振するがゆえに成り立つ、都市ならではのひとつの神秘空間かも知れない。
ただ、いずれにしてもそこでは両足で大地に立つという感じではない。「世界の中心・・」でなくても良い、どこか空気のいい、小高いところで星空を見上げてほしい。じっと見つめているといつの間にか自分が無くなりそうである。きらめく星達の中でまず目にするのはやはり北斗七星であるが、最近感じるのは、その北斗七星の形がどうも変化しているのではということである。宇宙時間からしたら、たかが何十年なんかは一瞬のはずなのだが、なぜか動いてるのである(気のせいか)。何十光年もの距離で、気の遠くなるような時間の流れの中、宇宙は少しづつ動いている。恒星と恒星間というよりも太陽系と何々系というレベルで動いている。意識的に星間の闇にじーっと目を凝らすと、またも吸い込まれるようにそこにも無限空間が広がる。確かに宇宙は無限だ。その中のどこかに地球と同じ様な生物がいるかもしれない。とすれば、そこから宇宙規模でグーグル的逆照射すると地球に行き着き、日本に行き着き、大阪のどこそこ行き着き、その中の一人に行き着く。しかし、そこからさらにその人の心を覗くと、ブラックホールのごとくそこから「精神」という無限の神秘世界が広がるのである。すごい。ただ実際目に出来るのはその前段階の「現前」、世俗的な人間模様だけだが。この宇宙の壮大なスペクタルの中、究極には、人間(人類)の最高の「作為」が建築物(建造物)だとしたら、建築こそミクロな心の宇宙の神秘とメガマクロな宇宙の神秘をつなぐ「神秘のアンテナ」として厳然たる存在でありうるのだろう。果たして現代のモダニズムは世俗を超えた厳然空間を勝ち取りうるまで発展出来るのだろうか・・・。
メキシコ 國際コンペ
メキシコ独立200年、革命100年記念コンペに参加しました。
締め切りは2月1日必着。航空便ということもあり早めに出そうということで、無事昨日作品の発送が終わりました。
基本的課題はモニュメントの建立ですが、公園を含めたその地域全体を見通し、野外劇場等も提案するというものでした。
メキシコには、だいぶ前ですが一度、ティオティワカンやモンテアルバン、パレンケ等の遺跡を見に行きました。そのためもあり、友人の建築家からその情報を聞いたとき即参加してみようと思いました。ただそれが昨年末だったので、いかんせん締め切りが迫っていました。いきおい「やっつけ」になりがちですが、スタッフはじめ良い協力者のおかげで何とか乗り切りました。これは二段階コンペで、ファイナリストに5人が選ばれます。朗報を待ちます。
渡辺豊和 特別記念講演
日時 2008/1/26(土)午後4時-6時
場所 京都造形芸術大学
渡辺豊和氏の京都造形芸術大学退職記念講演が上記にて行われます。
長年の教授職における、幾多の学生達の育成。また同時に建築家としても多くの作品を作ってこられた氏の今回の記念講演は、一卵性双子のように密接な関係であった二つのフィールドからの、一区切りとなる興味深い講演になると思います。
(興味のある方は大学の方へお問い合わせください。)
謹賀新年
明けましておめでとうございます。
年賀状をお出し出来なかった皆様には
この場を借りてのご挨拶とさせていただきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
建築を取り巻く環境は、ソフト面、ハード面ともども、
ますます混迷を深めていくであろう2008年です。
どこまで将来を見据えれるかはともかく、しっかりとした
もの作りの基盤は失わない気概だけは維持したいものです。
今年の合言葉は「チェンジ」でしょうか、内外を問わず。
特にアメリカの「オバマ氏」によってその象徴を見たいものです。