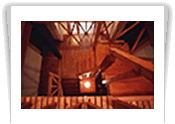新年明けましておめでとうございます
新田アトリエは本日より、2006年の活動を開始いたします。
旧年お世話になった皆様には、本来なら直接お会いして、新年のご挨拶をすべきなのですが、この場でのご挨拶をどうかご了承願います。
改めて、皆様本年もどうぞ宜しくお願い致します。
2006年の最初お知らせは、昨年末にお知らせした通り、1/14のオープンハウスです
また、2月20頃にはこれも昨年オープンハウスをしました、ステルスⅡが新建築(住宅特集3月号)にて発表される予定です(その折には、きちんとお知らせします)。
オープンハウス
来る2006、1,14(土曜日)オープンハウスを行います。
この建築は大阪市内に建つ大変小さなものです。間口一間半(2700)、奥行き役13mの長屋切り取りタイプ、木造2階建て。おまけに当然のように超ローコストという設定です。当事務所では初めての、外壁サイディングを使った(使わざるを得なかった)普通の住宅への挑戦でした。小品であることもあり、ステルスⅡのような大々的なオープンハウスにはしませんが、もしご希望の方が御ありでしたらメールにて申し込み下さい。
傷菜
横穴や竪穴住居という始原的住処はともかく、18世紀フランスの建築理論家「ローゼェ」により命名された「原始の小屋」という建築(建物)が、西洋建築史上での初源的空間と言われる。そこから円柱が生まれ壁が付けられていったという論理である。その素朴な時代から何千年後かの今日、人類はバベルの塔ならぬ超高層建築、果ては宇宙ステーション建築の実現に至るまで、人類の「絆」と共に建築の「絆」をこぎつけた。人類のこの計り知れない英知、エネルギー、生命力には驚嘆するばかりである。その一方でこの有限な地球資源、環境を食いつぶし過ぎて、無限な開発への警告を自ら発するようになった。人類のこの功罪をどう評価するかは幾多の優秀な人類学者にまかせるが、これにはどうも、他の動物には無い人間独特の性癖、「欲」のDNAが起因しているようである。
本来、人類、人間が成長する、成熟していく過程においては、必ず捨てていかなければならないものがある、いわゆる「脱皮」である、なぜなら、一個の物体は全てを抱え続けては生きていけない、よしんば抱えたままいても、生命体の死とともに放り出さざるを得ないのである。ならばそれまでは抱え続けようという気にもなろうかも知れないが・・。
ともあれこれは各個人の生活、人生観というものに如実にあてはまる。一生の内に違う生き方は出来ない。いろいろな実体験のシュミレーションをした後に一つを選ぶことは出来ない。一発勝負なのである。だからこそ、皆出来るだけ「読み」を利かそうとする。慎重の上にも慎重に「利」を抱えようとする。翻るとそれが異常な保守主義(優勢種の保存主義)を産み、成熟の上に完熟、さらに潔癖を目指そうとするのである。この性癖がまずは生存の源である食物へ向かう。
たとえて言えば資本主義経済が定着した近来、農家で収穫される野菜類一つとっても、見た目はほとんど変わらないのだが、どこかちょっと傷でもあろうものなら、それは出荷できずに捨てられるという。そういえば小さい頃、父親ときには祖父につれられてよく「マツタケ」を取りに行ったのだが(その頃はまだ良く取れていたのか篭いっぱいになったと言って喜んでいた)、そのおりもちょっと欠けたものや、傘が開きすぎたものものは刎ねて仲買人(今思えば)に渡していた。残ったそれらは家で焼いて食べていたから非効率ではなかったが。まあこれらは「商品という市場価値観」優先社会でいえば当たり前かもしれないのだが・・・。また昨今の狂牛病問題をみても、念には念を入れる日本人は特に潔癖性のようである。
しかし一方で、最近は薬業界の規制緩和でゼネリックが普及してきたし、建築界での、最近流行のリフォーム産業などは、そういう、人間が抱える完璧、潔癖主義への反省というか、心のゆり戻し感が働き出したとも見て取れるのではないか。古くなって傷ついた古材を大事に使っていく、あるいは手を加えて古色を蘇らせる。傷ついた野菜「傷菜」と一緒で、見た目は悪くとも味がいいのである、「味」があるのである。ただし、これ見よがしのビフォー・アフター(テレビ番組)まで行くと本来の「匠」という日本古来の職人業、名人芸が安っぽい言葉に格下げされたようで悲しい現象ではある。
お礼
12/10のDO・SEMIの講演会及び展覧会が盛況(?)のうちに終了しました。うまくいったかどうかはよくわかりませんが、来てくださった皆様、ご清聴ありがとうございました。この場をかりてお礼申し上げます。また大阪工技専の二部の学生諸君の熱気には非常に好ましい感じを持ちました。今後も頑張ってください。
涙・・1 (さすらいの建築侍)
キラ星のごとくの有名女優がスクリーン上で見せる涙(例えばイングリッド バーグマンの「たがために鐘は鳴る」等、古イカ)は限りなく美しい、特に悲しい涙にまた人々が涙する。これに限らず「涙」にはいろんな涙がある。考えてみれば人間は赤ちゃんのときが一番よく泣く(涙する)。「泣く子は育つ」ともいわれる。それから成長するにつれてだんだん泣かなくなる、親からも「男の子は泣いちゃいかん」、「女の子みたいにメソメソするな」と言われたりする。(ということは女の子は泣いてもいいのかな?)とにかく大人になるにつれてなかなか泣かなくなる(泣けなくなる)。この頃はこれまた「男は人前で泣くもんじゃない」などとも言われる。だから男は青年期から壮年期にかけて泣かないでしっかり働く。そしてだんだんと年をとってくると、今度はだんだんと又涙もろくなるという。この現象論には誰しも異論はないだろう。しかしこの相関関係にはもう一つ意味があるのです。というのも涙の量をY軸に年齢をX軸にすると、明らかにプラスの2次関数曲線を描く、しかしそれに逆比例して、量が減る分今度は涙自体の意味性、内容性が重くなる、または高まってくるのです。これがもう一つのエネルギー保存の法則(といえるのかどうか?)だと思うのですが・・。この人間(動物)に備わった絶妙なバランス機能(メカニック)が、人類をここまで永らえさせている最大の要因だと言えるのではないだろうか。
そうです、この法則は何にでも当てはまります。例えば作家、芸術家といわれる人達、小説家、画家、音楽家、そして建築家然りです。共通しているのは制作量と質の相関関係ですが、先の「涙」曲線と違うのはカーブが逆転していることです(マイナス2次関数曲線)。青、壮年期に仕事量が増えピークを向かえるからです。しかしここで先程と逆の内容的反力が働きだします。良くいわれる「筆が荒れる」現象です。書き(描き)過ぎて、また作り過ぎて、質、内容が薄れていくことです(勿論例外もありますが)。ただ建築の場合はまだ、優秀なスタッフを増やせば大丈夫ともいえそうで、現に売れだすと、アトリエ派から組織事務所への必然的「脱皮」が図られます。しかし、これがなかなか想定内(質、内容的に)に収まらないところが世の中の面白いところです。この移行過程、あるいは移行後の失速(失礼)パターンは枚挙に暇がないのですからー・・・・残念。・・・とはいうものの拙者、雨の日は憂鬱です、靴底から「涙」が滲んできますからー・・・<売れたい>斬りー・・・。