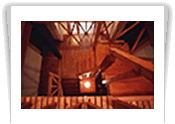DO・SEMI<いよいよ登場です> 地と図もしくは主to従・・(2)この会議中でのひとコマが、何故それほどトラウマのごとく脳裏に焼きついているのか。これは私の中で、このエピソードを序章として、その後加速展開されたCAD、CGの進歩、またIT革命による社会のコミュニケーションシステムの劇的変化を観たがゆえに、その助走期であった当時、この予兆を見透せなかったことがよほど悔やまれているのだろう。それはまさしく「地と図」の転換が起こったような感である。さてここからが本題だが、こうした社会環境の変化により、人間の思考や価値観がどのように変わるのか、其れが又逆に建築デザインを良くも悪くもどのように変えて行くのかを考えたいのである。確かにツールの進歩は建築界に有形無形の多くの進化をもたらした。とりあえず解りやすい変化、進歩というところでいえば、「伊藤スクール」を筆頭(日本では)に圧倒的に展開される軽妙なプランと形態等なのだろう。ただこれらはあまりにも楽観未来主義「的」過ぎて(勿論理念ありきなのだろうが)、私のような田舎者には満足しうる理想系としては物足りない。ファッショナブルな、いかにも脱理念的な足早性という表層が見え過ぎてしまうからである(だからこそ人気なのだが)。やはりツール革命ではだめなのか。では正真正銘の革命ではどうか。たとえば現在のロシア。1991年にソビエトからロシアに変わった。1917年の社会主義革命から70余年続いたソビエト国家の終焉だった。ここでも「地と図」、「主to従」の転換である、封印されていたロシア正教の復活でもあったのだから。このころから盛んに言われていたのは(私の周りでだが)、新しいデザインが、新革命下のロシアの若者達から現れるだろうというものだった。確かに程なくして、「AAスクール」が活動の中心だったろうが、若きロシア建築家旋風が吹き荒れた(特にコンペで)。スワッ、第二次ロシアアバンギャルドか、それだけ彼らの出現はセンセーショナルであり、黒い稲妻のごとくみごとなドローイングが魅惑感を迸らせていた。それから彼らがどう期待どうり活躍したのか、そのドグマがどれほど流布したのか詳しくは知らない。洗練された北欧モダニズムとは違うより寒い国からの照射だからこその期待であったろう。ただ少なくとも現状からすると一時期のブームの域は超えていないのか、彼らの眼差しは何処へ向ったのか・・・。しかし個人的にはまだまだ十分期待している。となれば次は何処なのか、何なのか、このへんは[親鸞的他力本願」としてちゃんと注目すべきだが、しかしやはりここは自力でやるしかないのか、タイヘンだー。いやいや日本の若い皆と共にやろうではないか。 M氏に哀悼ますます大きな問題に発展しているこの度の構造計算書偽造問題。個人的には前回発表したコメントで終わろうと思っていたのですが・・・・。当時者の一人である元受設計事務所のM氏の死という最悪の事態を迎えてしまいました。これには私も含め同業の設計事務所の人々に新たな衝撃が加えられたのだろうと思い再度入稿しました。悲しい事実です。まず苦しみの中で自ら命を絶った(と言われている)M氏に心より哀悼の意を捧げます。勿論それによってこの問題が解決した訳でもなく、彼の罪が消えることもありません。ましてマンションを購入された住人の人達の怒りが納まる訳でもありません。また、勿論私がこの問題の詳細を知る由もなく同業とはいえM氏を知っている訳でもありません。したがってこの一コメントが何の足しにもならないことは承知です。にもかかわらず再入稿したもう一つのきっかけは、NHK教育で「故吉村順三氏の作品について」をやっていて、その中で、普通はありえないことですが、今回の事件について言及していたからです。こうした番組であってもあえてつい触れざるを得ない状況だということでしたのでしょう。これはどちらも同じく「建築」なのです。この同時性、「建築」が芸術と技術の両義性と経済とのアポリア(矛盾)を抱えた社会的産物であるということを、多くの人に改めて認識してほしいと思ったからです。 地と図もしくは主to従・・(1)いまから17,8年程前から始まってほぼ10年間、毎年場所を変えて行っていた集まりがあった。「戦後生まれの建築家100人展及建築デザイン会議」というものである。この「運動」に参加した集団が今や日本の現代建築家の主流になっている。この時の活動内容をここで紹介するには適任ではないので、興味ある方はネット等で調べていただきたいのだが、大変刺激的でその後の社会及び建築シーンに多大な影響を与えたと思っている。毎年変わるテーマ、場所だがいつも、前後の全体シンポジュウムと夜を挟んだ2回の分化会という構成だった。その中での一つの分化会でのことである。何年めの会議か、場所が何処だったか、その辺は今はっきりとは思い出せないが、ここで、時代に対する認識力の大切さを忘れないための、自身への見せしめのように記憶しているシーンがある。その分化会は難波和彦氏(現東京大学教授、建築家)が座長であり、そこに私も出席していた。ここでのテーマ、タイトルも思い出せないのだが、難波さんがしきりに国家予算のことや21世紀的日本経済の展望とそれに対する建築家のあり方のようなことを力説していた(間違っていたら難波さんごめんなさい)。詳しい資料をみれば解ることなのだが、その詳細をお知らせすることが主題ではないのでご了解願います。その分化会のなかで、確か難波さんの友人の建築家(名前は忘れました、ごめんなさい)だったと思うが、ツールとしてのCADコンピューターの話をされていました。当時はまだまだ手書き全盛(ということは初期ごろの会議ですね)だったので、頑なに鉛筆手書き有用説を支持していた。コンピューターは直線は書けるが自由曲線は無理でしょうと食い下がっていました。しかし其の人は、いやいや曲線も自由ですよといとも簡単に説明されました。難波さんもその辺はご存知のようでその人に同調します。当然ながら、メイン課題はそんなツールの問題ではないので全体はさっさと本題に戻って行った。これは何ということのない一コマのエピソードだが、私には、その時の本題は忘れても、この時のやり取りだけがトラウマのように記憶されている。(続く) Qチャン おめでとう高橋尚子選手の復活を心より祝福いたします。 |