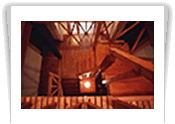心のシャッター通り
初めて知ったが長崎、佐賀にまで新幹線を通そうという話があるらしい。そのための賛否を競った市長選挙があり、幸いにして(?)反対派が勝利をしたと言う。また少し前には岩国市の市長選挙もあった。ここでも米軍再編計画に伴う政府案を受け入れるかどうかが争点となり、政府案反対派が勝利した。勿論この二つの問題を一概には同じ土俵に挙げられない。方や地方再建、方や外交問題が大きく影響しているからだが、ただどちらにも共通しているのは経済問題である。いわゆる「お金を落とす」というものである。ますます東京一極集中国家になろうとしている、「島国日本」としては、自国でのドーナツ現象型経済にまだまだ頼らざるを得ず、低迷していく地方としてはいわゆる「お上のお金」の魅力が捨てきれないものとして(図式として)歴然とあるのである。貧乏しても独立独歩で行くべき(まるでカストロ首相のように)だという人達とせっかく落としてくれるというものをわざわざ拒まなくてもいいのではという人達もまたいる・・・。
大事なことはこれが「国家ビジョンの入れ子」になっているということである。
今や地方のアーケード、シャッター通り問題の深刻化はカシマシイ。しかし人々の心の中に、華やかな六本木ヒルズ族の飽食に反比例した「心のシャッター通り」を作ってしまうことだけは避けるべきはずなんだろうが・・・・。
盗作と類似性
若い画学生が、ルーブル(美術館)等で名画の模写をする姿は好感が持てる。しかし今回、洋画界の重鎮?W氏の犯した盗作行為は、人間が持っているおそらく最高の資質の一つであろう創造性の領域でのことだけにおそまつである。本人はもとより、それを取り巻く日本の優秀な見識者達も恥ずかしい。この根底、領域には製作者のモラルに対する「性善説」がある。何やらちょっと前にどこかで聞いたようなフレーズだが、「人の振り見て我が振り直せ」より「二度あることは三度ある」か、ということわざがつい口をついて出てしまう。どちらにしても人間の中に抱えている悪魔性は油断すると必ずどこかで出現してしまう、それを抑えるには普段からのそうした「ことわざの伝承」が自己抑制を図るのに役立つと代々言われてきた、少なくとも最近までは・・・。
今回のようなあからさまな件は論外だが、この創造性、オリジナリティーという代物は確かに厄介なものである。日本の建築界でもこれに似た話は昔からよく言われていた(ここでは誰とは言い難いが)。その場合のパターンも全く良く似ている。海外に旅行、留学してきて、たとえばそんなに遠くの、また田舎の建築だからばれないだろうと思い、ついつい真似てしまう。それは情報量の問題だから、昔は危険性も少なかったのだろう。厄介だと言ったのは、建築の場合、「影響を受ける」と言うフレーズはれっきとして存在していることである。これはいってしまえば世界中の建築にあてはまる。たとえば木造の法隆寺と石造のギリシャ神殿のエンタシスに見られる類似性、影響性云々、というものである、しかし影響を受けて、そこから独自の世界を生み出そうとするのは真摯な創造性への挑戦で良い、しかし何回も言うが今回のようなあからさまな盗作者は即座にペンならぬ筆をおくべきであろう。
身近な所では、少し前になるが、友人の建築家が、自分の作品が若い建築家によって盗作されていて、その彼のホームページで、あたかもその本人の作品として掲載されていたということがあった。その時も法的な措置を取ろうとしたのだが、弁護士との相談では、その写真が小さなワンショットだけなので、どこまでその真意を問いただせるのかが難しいと言うことになったと聞いた。
これには落ちがある。その時の話題は、その「盗作者」がよりによって、僕の弟子だとそのホームページ内で書いていたと言うのである。これにはまいった。真相は学生時代に確かに教えた(授業で)学生だったのだが・・・。弟子を名乗ってくれるのはいいが、もっといい話題になるように使ってほしいと切に、切に祈ります。
ロックンローラーと「ネ萌え建築」
モダニズム建築の一つの目標がレス空間、極限すれば解脱空間にあるとしたら、それは永遠の目標選択であり、またそれに向かう建築家が一人の求道者であるならそれはそれで間違いではない。また建築が本来的に、社会資本的産物であるとしたなら、20世紀モダニズム建築はその指針たりうるリーダーシップを担おうとしたのは明白である。しかしまたそれはもろ刃の刃を研いだことにもなる。合理性の追求は新芸術と共に均質化主義を台頭させた。
人間は生きるうえになんらかの理由を抱えている。理由の上の生存のために、家族のために、愛する人のために、国のために、仕事のために、芸術のために、人一倍稼ぐために、理不尽なシステムのために、もしかしたら憎むべき人、対象のために、時代を克服するために・・・。とすればその人間及び人間社会が作り出す建築も思いを共有する羅針盤であろう。歴史的な建築界のエポックがある。日本が第二次大戦の敗戦ショックを克服するためには、(軍国主義的保守主義を払拭するためには)、戦後まもなくの国内コンペ(広島平和資料館)で、先ごろ亡くなった丹下健三氏が、いち早く開示してみせたモダニズム建築の爽快感が、国家的にも、思想的にも、国民的にもそのニュートラルさが、皆一様に共振できた新日本ルネサンスの幕開けとなったのである。
この、建築にとって幸せな時代をベースにした戦後建築は、先の丹下スクールを筆頭とした大モダニズム旋風として近代日本を再建、再生すべく順風漫歩に歩みを続けてきた。その中で、唯一の抵抗というか逆風が、先ごろ収まった?「ポストモダン」運動である。
これは合理化とともに抱えこんだ均質文明主義へのアレルギー現象として、言い換えれば建築界のロックンローラーとして、一大革命的現象を見せた。それはまさに、原点主義、初源主義、一般には「コスモロジー派」といわれたいわば「もだえる建築」達であった。くしくも日本でのそれは、いわゆる団塊の世代を最後尾に従えていて大変な潜在的推進力を備えていた。その証は、かの丹下さんですら、晩年その論理影響下で代表的な仕事(新東京都庁)を成し遂げている事を見てもわかるだろう。私にとっても、それがちょうど建築家としての駆け出し時期に重なっていたから、大変新鮮な刺激を受けたものである。(それが高じて、まったく資質が違うにも拘らず、ポストモダンの旗手であった渡辺豊和氏に私淑することになった。)
しかし、それが20世紀の終焉と共に、バブルの副産物であったごとくの在らぬ疑いというか位置付けをなされ、少なくとも現代日本では葬り去られてしまった感がある。しかし「建築産業」は時代と共に流行するが、建築そのものは、それが創造性に富んだ空間であれば必ずや、流れ行く時代を超えて評価が維持されるであろう。いや逆に、日本が世界の近代建築シーンの中で、「唯一」誇れるの近代オリジナリティーだとして再評価されるやも知れない。
少なくとも、ますます合理主義社会に突入していく現代社会にあっては、ネオポストモダンのビジョンのもとに、単なる造形主義を超えた「ネオもだえる建築」、略して「ネ萌え建築」を模索し続けなければならない。
それでも山河は青々と
歴史のなかの自然と人間の歩み、この二人三脚(?)は案外旨くいくのかもしれない。営々と築いてきた文明の綻びを「ハルマゲドン」のごとく危惧することもないのではないか。考えてみればあの栄華を誇ったローマ帝国ですら崩壊した。しかし現代でも陽気なイタリア人は、相変わらずキザなナンパ野郎?いやサッカー好き野郎である。勿論そう簡単に楽観論者になった訳ではないのだが、人間の刹那を横目に確かに自然も営々と生きている・・・。
決まって年一回の行事は、寒い、暗い冬の帰省であった。しかし今年はめずらしくこの連休に帰って来た。名目は一人ぽつんと暮らしている母親が、珍しく体が調子悪いというから見舞がてらではあったが。何年ぶり、いや記憶にあるところでは何十年振りかもしれない。相変わらず不精で帰っても何をするわけでもないのだが、いつものように近所をうろうろした。冬と違って、畑やら田植えやらをするわずかな村の老人達に出会う。遠くからどちらからともなく軽く会釈はする。しかし今や見知らぬ人間になってしまっているのだろう。当然のように[よそ者]
を見るいぶかしげな視線が痛い。それはともかく、またそれを含めて、やはり冬とは何かが違った。空気が違う、空が澄み切って青いから当たり前だが、新緑がやたら目に眩しく新鮮であった。冬眠から目覚めた熊のように自然が生きずいている。
それとともに今更のように自然の生命力を感じる。今や誰も通らなくなった小学校への小道は、見る影も無く獣道というか雑木林に変貌している。川も川でなくなり、もはや「溝」に近ずこうとしている。まだわずかに残っていた地道もヒノキやスギが成長し空を覆う。この薄暗い林のトンネルで思わずセンチメントな涙があふれてきた。あわてて誰かに見られていないか前後を振り向く、一人だと思ったら安心したようにまた涙が出てきた。人間の営みとは何なのか、人間は何をしているのか、お前は何をしているのか。逃げるように、抜け出すように都会に出て行ったお前は、それに変わる何を得たのか、何を求めたのか、果たして誰を幸せにしたんだ。結局何も変わってはいないではないか・・・。
戦後の喧騒からしばらくしてからとはいえ、あきらかに50数年を目の当たりにしてきたこの村の何が変わったのか。確かに道路がアスファルトになって、断じて頼んだわけではないのに、情緒があった曲がりくねった道がまるで悪童を矯正させるように広く真っ直ぐな「県道」に変わった。だんだん畑も、棚田も限りなく野原へと近づいてきた。そうなんだ、近代的になった道路だけが我が物顔でまかり通っている。しかしそれに反比例するかのように傍らの人間はいなくなり、ついに人間の証自体がなくなり、皆、その道路までにも迫るように自然に帰っているのだ。くしくもその夜、「宮崎駿」も話していた。人間の営みの愚かさと喜びを、格差の助長も日本人の人口減少もそんなに心配していないことを、たとえば地方の過疎化はもう一つの自然再生への営みなのだと・・・、そうまさに全ては寡黙な営みなのだ。
それでも、愚かにもまだまだもがくのか、もうすぐ友人O氏の死から4年目が来る・・・。
バナキュラー・ニヒリズム・モダニズム
バナキュラーとニヒリズム、表現の世界でこの二つを同じマナ板に乗せるのはタブーとされる。しかし人間の心には根底的に、こうした一見相反する二つのものが同居している(形而上的見地)。たとえば静かな安心を欲する心と、変化を欲する心といえば解りやすいかも知れない。こうした言われ方をするところでは、ジキルとハイド、天使と悪魔、20世紀絵画でいえば写実主義と超現実主義、アメリカ文学でいえばヘミングウエイとヘンリーミラーとでもなろうか。いずれにしても、こうした両極的現象は表現の世界に限らず現実社会でもすでに同居している。繰り返すが誰しもどちらかしか持ち合わせていないのではなく、どちらも潜在的に持っている。ただ個々の表現の時々ではそれらが平等に顔を出すのではなく必ずどちらかが勝ってしまう、いや勝たなくてはひとつの意思を持った表現にならないからである。20世紀モダニズムは、ある意味その間隙を縫って(両方を具有する面をある時々、瞬間見せるがゆえに)イニシアティブを獲得したのである。勿論それらはどちらの方が優れていて、どちらの方が劣っているということではない。それは表現の世界の役割がなんであるのかを問うてみればよい。様式論には決着ガついたかに思われている21世紀世界においても、実は多様なシチュエイションとニーズに溢れているのだから。
ではそれらはどのような時にどのような方法論によって表出されるのか、また必要とされるのか。それは当然その表現者個人の内面の在り方によるところが大きい。しかしそれがまた個人を取り巻く環境、関係性によって左右されている。そうするとあとはそれがどのように自身の琴線に触れるかだが、これはまた多種多様な神経回路に満ちていて複雑である。最後に行き着くところは論議を超えた、きわめてシンプルな感受性の問題になる。しかしここではあえて二つのモチベーションのあり方を上げておきたい。一つは内因的なもの、精神医学でいうトラウマのようなものである。多くの表現者は基本的にこれを引きずっていると言っても過言ではない。言い換えれば最初から備わっている一つの負荷でもある。そしてもう一つが外因により誘発されるものである。たとえば20世紀は戦争の世紀であり、多くの表現者がその衝撃から筆やペンを取っている。ピカソやダリはスペイン内乱を目の当たりにして宿命的にキャンバスに向かったのだし、ミースのモダニズムはユダヤ人であるという歴史的内因とナチスという最悪の外因により作れ出されたニヒリズムの結晶でもある。たとえば日本でも、これは逆に外因が筆を折らせたという例だが、阪神大震災によって日本の「デコン」は終わったといわれる、それだけあの時の衝撃は生半可な表現を押しつぶしたのである。
いずれにしても表現者には、この内因、外因のどちらか、もしくは両方がからまって、自身のポジション、社会義務の枠を超えてでも表現しなくてはいられない気分の高揚、または表現しなくてはならないという自己哲学の突き動かしが必要とされる。その意味からすると、これはひとつの「アウトサイダー」のなせる業なのであろう。